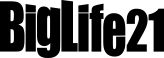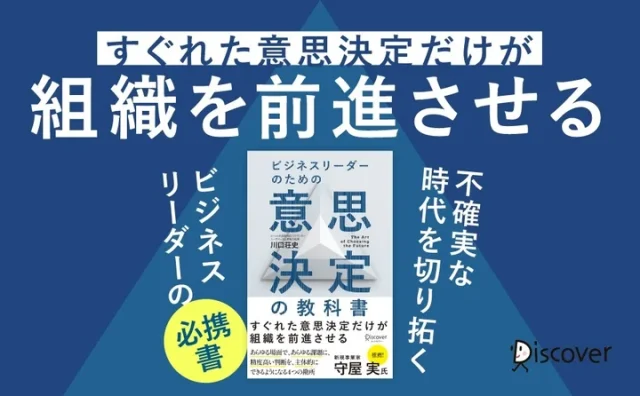B to Bブランディングで足りないのは、技術ではなく恋愛経験だ
イマドキのビジネスはだいたいそんな感じだ! 21
B to Bブランディングで足りないのは、技術ではなく恋愛経験だ
◆文:佐藤さとる (本誌副編集長)
 「引き寄せの法則」ではないが、ブランディングのことを書いたら、ブランディングの相談を非公式に受けた。
「引き寄せの法則」ではないが、ブランディングのことを書いたら、ブランディングの相談を非公式に受けた。
直接の相談内容はブランディングをどうにかしたい、ということではない。その企業=仮にA社としよう=は中京地区にある自動車関連の部品をつくり続けてきた典型的モノづくり企業でものすごい技術集積がある。
A社は、この「ものすごい技術集積」を活用して新規事業に結びつけることはできないかと、専門部隊をつくって4年ほど活動したものの、目に見えるような成果を挙げられないでいた。そこで「何か自分たちの技術を紹介する効果的なプレゼンツールが必要だ」と考えた。
たとえば、「ストーリー仕立てで自社技術を紹介する」「よりわかりやすく自社技術を紹介する」「技術を動画で紹介する」というのも「いいんじゃないか?」という。…う〜ん。
たぶんこのやり方、この考えでは新規事業の果実はきっと結ばない。なぜか?
自社技術を分かってもらおうとしてばかりいるからだ。
「そのための事業部隊なのだから、当たり前だろう!」
お叱りを受けそうだが、この当たり前だと思っていることが、まず落とし穴である。他社との新規事業は結婚相手を探すようなものだ。相手が「その気」になっていないと難しい。
最近の技術はかなり専門化している。親しいようでも手法や分野が違っていれば、そこで交わされる会話は日本語とウルドゥ語くらい違う。
中小企業に希望を与えたドラマ「下町ロケット」は、大企業の帝国重工と中小企業の佃製作所のエンジニアが、「純国産ロケットを打ち上げよう」という共通の強い思いがあったから実現した。つまり最初にテーマがあってそれを実現するためにお互いの技術を持ち寄ったのだ。
その「実現したい強い何か」が共有されていない限り、いかに優れた有名企業が「この技術と御社の技術をコラボして一緒に“何か”創りませんか?」と言っても相手はポカンとするだけだ。
技術は何かを実現するための手段に過ぎない。つまりA社の人たちは順番を間違えてしまっているのだ。これはB to Bのメーカーにありがちなことだ。
そもそも現実の下町ロケットは、テレビのようにはいかない。たとえば、下町ロケットの深海版でもある東京・葛飾の中小企業が実現した「江戸っ子1号」では、下町企業同士の激しい鍔迫り合いがあった。それをなだめ、諌め、眇めつ、繋いでいたのは、実は地元の信用金庫だった。
いざ実現しようとなると、腕に自信のある企業同士は「オレが、オレが」となるものだ。
ではどうすればいいのか。
1つは、自社の技術でできることを「相手のフィールドで実現してしまう」ことだ。
たとえば、繊維業界が水道業界に入りたいと思うなら、従来の水道管に代わる水道管を実際につくってみせることだ。もし畜産業に入りたいなら、新繊維を使ったサイロをつくってみせるのだ。ワタシと結婚したらこんな生活ができますよ、とアピールするのである。
もう1つは技術の粋を集めたシンボルを生み出すことだ。江戸っ子1号はその典型だ。細かい技術の説明より「6500メートルの深海」でも「耐える」「作動する」ことがリアルに分かれば、それで十分である。歌手としてミリオンセラーを出した、アスリートとして世界大会に出たといった“誰もが納得する”圧倒的魅力だ。
そしてここの大きなポイントは「江戸っ子1号」という技術力をイメージできるわかりやすいネーミングを行ったことだ。
こうやって醸成されたイメージは、情報の受け手の脳のなかで勝手に結ばれ、一人歩きをする。
「素敵だ! そんなスゴイ技術を持っているのなら、ウチのこういった製品にも応用できるかもしれない─」
この結ばれた像の積み重ねがその企業の、その技術の、その製品のブランドをつくっていく。A社のスタッフはもしかしたら恋愛経験が圧倒的に足りないのかもしれない。まず磨くべきは、製品技術ではなく、恋愛技術なのだろう。
イマドキのビジネスはだいたいそんな感じだ。