

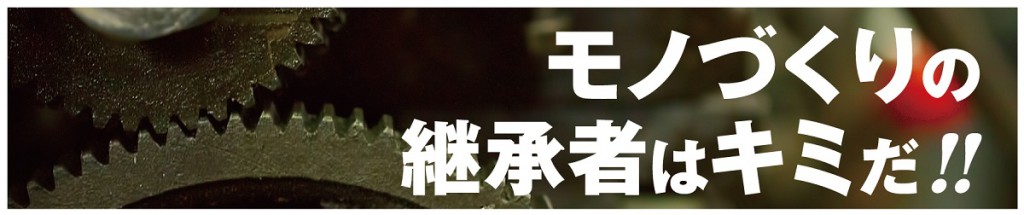


三櫻製作所 大友冠代表 「いまの子たちは感動すると一所懸命やります。だからいかに感動してもらうかが、私たちの仕事なんです」と語る三櫻製作所代表の大友冠氏。「仕事を教えるだけでなく、いまの子供たちの食生活や家庭環境も考えて、学校の先生方と協力しながら育てていくことが大切だと思います」
 「今はやれることはまだまだ少ないですが、いずれは設計とNCマシンのプログラム全体をやっていきたい」(デュアルシステム科OB山崎さん)
同社は自動車メーカーのマザー工場の心臓部に使われる研磨材など、加工機械や精密機械などの部材を受注生産する。いわゆる下請け工場だが、ダイヤモンド研磨技術では知る人ぞ知る存在。取引先はいずれも世界的工作機械メーカーばかりだ。
「今はやれることはまだまだ少ないですが、いずれは設計とNCマシンのプログラム全体をやっていきたい」(デュアルシステム科OB山崎さん)
同社は自動車メーカーのマザー工場の心臓部に使われる研磨材など、加工機械や精密機械などの部材を受注生産する。いわゆる下請け工場だが、ダイヤモンド研磨技術では知る人ぞ知る存在。取引先はいずれも世界的工作機械メーカーばかりだ。
 その精度は1000分の1ミリ以下。耐久性は数万台分だ。こうした高い精度を確実に出せる職人は実は世界的にも少なくなって来ている。機械加工メーカーの合従連衡が続き、高精度高品質を誇った欧米の工作機械メーカーが1つまた1つと消えていったためだ。代わって日本の工作機械メーカーが台頭する。つまり三櫻製作所のような町工場の職人技術が、世界のモノづくりの根幹を支えているのだ。
その技術をデュアルシステム科卒の若い職人が継承する。
大友氏は「これで100年企業を目指せる」と期待を寄せる。「数年前に息子が入って後継体制はできたが、100年企業にしていくためにはどうしても息子の脇を固める職人が必要だと思っていたんです」
とは言え、いまの若者がどこまで関心を持ってくれるのか、どう育てていけばいいのか不安だったと吐露する。昔のように「盗んで覚えろ」というやり方は通用しない。同社の世界的技術は最高5次元の高度なNC工作機械の制御技術に支えられているが、「モノづくりの基本はまず手仕事だ」と大友氏。
その精度は1000分の1ミリ以下。耐久性は数万台分だ。こうした高い精度を確実に出せる職人は実は世界的にも少なくなって来ている。機械加工メーカーの合従連衡が続き、高精度高品質を誇った欧米の工作機械メーカーが1つまた1つと消えていったためだ。代わって日本の工作機械メーカーが台頭する。つまり三櫻製作所のような町工場の職人技術が、世界のモノづくりの根幹を支えているのだ。
その技術をデュアルシステム科卒の若い職人が継承する。
大友氏は「これで100年企業を目指せる」と期待を寄せる。「数年前に息子が入って後継体制はできたが、100年企業にしていくためにはどうしても息子の脇を固める職人が必要だと思っていたんです」
とは言え、いまの若者がどこまで関心を持ってくれるのか、どう育てていけばいいのか不安だったと吐露する。昔のように「盗んで覚えろ」というやり方は通用しない。同社の世界的技術は最高5次元の高度なNC工作機械の制御技術に支えられているが、「モノづくりの基本はまず手仕事だ」と大友氏。
 「旋盤などの手仕事の技術をしっかり覚えてもらってから、コンピュータに行く。原点が分からないといくらプログラムができても、モノはつくれない」
基本は「手作業をよく見ることと聞くこと」だ。最初は手作業のポイントを見てもらう。道具の使い方から砂の付け方。作業ごとの体の使い方も教える。
「それと音や振動。やっぱりモノづくりに関心のある子たちですから、分かるんです。こんな音がした時にはこんな抵抗があって、切削の刃がやられるぞとか。そうやって何か発見があったりすると感動するんですよ、彼らは。だからいかに感動して貰えるかを考えました」
「旋盤などの手仕事の技術をしっかり覚えてもらってから、コンピュータに行く。原点が分からないといくらプログラムができても、モノはつくれない」
基本は「手作業をよく見ることと聞くこと」だ。最初は手作業のポイントを見てもらう。道具の使い方から砂の付け方。作業ごとの体の使い方も教える。
「それと音や振動。やっぱりモノづくりに関心のある子たちですから、分かるんです。こんな音がした時にはこんな抵抗があって、切削の刃がやられるぞとか。そうやって何か発見があったりすると感動するんですよ、彼らは。だからいかに感動して貰えるかを考えました」
 「モノづくりは粘りがないとできない。でも若い子は粘れないんです。聞けばコンビニ弁当ばかり食べているという。それじゃ粘れない。ちゃんとした食生活、食育についても話したりするんです。でも先生方に聞くと今の子たちはそういう子が多いんだそうです。というのも母子家庭など家庭環境が必ずしも恵まれている子ばかりではないから」
大友氏は週に1度は食事に誘い出し、サッカーや野球の話など共通の話題を振っては生徒の生活環境を気遣う。
「やはり若い人を育てるには、先生から情報をいただきながら、生徒さんの親御さんと一緒になって面倒を見ていくことが大事だと思いますね。そうやって丁寧に見ていくと集中力がついてくる。こちらも教えがいがあります」
「モノづくりは粘りがないとできない。でも若い子は粘れないんです。聞けばコンビニ弁当ばかり食べているという。それじゃ粘れない。ちゃんとした食生活、食育についても話したりするんです。でも先生方に聞くと今の子たちはそういう子が多いんだそうです。というのも母子家庭など家庭環境が必ずしも恵まれている子ばかりではないから」
大友氏は週に1度は食事に誘い出し、サッカーや野球の話など共通の話題を振っては生徒の生活環境を気遣う。
「やはり若い人を育てるには、先生から情報をいただきながら、生徒さんの親御さんと一緒になって面倒を見ていくことが大事だと思いますね。そうやって丁寧に見ていくと集中力がついてくる。こちらも教えがいがあります」
 円高不況や大手メーカーの海外シフトなどで日本の町工場の閉鎖が相次いでいると言われるが、中小零細企業の最大の問題は後継者不足である。
大友氏はかつて仕事を受けると切削から焼入れ、研磨など8つの加工工程を腕のいい職人のネットワークで行なっていたが、「後継者がいなくなってそのネットワークが寸断されてしまった」という。
大友氏のもう一つの夢は、その寸断されたネットワークを再び構築することだ。ただ「一旦切れたものは復活しない。グローバル時代に対応していくには1つの工場が幾つもの工程を高いレベルでこなせないといけない。そのためには技術や職人をウチだけで抱え込むことではいけないと思う」
大友氏は、会社そのものを大きくしていくつもりはない。
「私は若い人を早く独立させようと思っているんです。そこから新しい協業関係を築いていく。求められているのはネットワークの再構築ではない。ネットワークの社会化なんです」
そのネットワークを繋ぎ、紡いでいくのがデュアルシステム科の卒業生の役割でもある。かつて、屋上から設計図面を紙飛行機にして飛ばせば、すぐに製品になって帰ってくるといわれた大田区。この町のモノづくりを次代に継承していくために、六郷工科高校と企業の挑戦は、この先も続く。
円高不況や大手メーカーの海外シフトなどで日本の町工場の閉鎖が相次いでいると言われるが、中小零細企業の最大の問題は後継者不足である。
大友氏はかつて仕事を受けると切削から焼入れ、研磨など8つの加工工程を腕のいい職人のネットワークで行なっていたが、「後継者がいなくなってそのネットワークが寸断されてしまった」という。
大友氏のもう一つの夢は、その寸断されたネットワークを再び構築することだ。ただ「一旦切れたものは復活しない。グローバル時代に対応していくには1つの工場が幾つもの工程を高いレベルでこなせないといけない。そのためには技術や職人をウチだけで抱え込むことではいけないと思う」
大友氏は、会社そのものを大きくしていくつもりはない。
「私は若い人を早く独立させようと思っているんです。そこから新しい協業関係を築いていく。求められているのはネットワークの再構築ではない。ネットワークの社会化なんです」
そのネットワークを繋ぎ、紡いでいくのがデュアルシステム科の卒業生の役割でもある。かつて、屋上から設計図面を紙飛行機にして飛ばせば、すぐに製品になって帰ってくるといわれた大田区。この町のモノづくりを次代に継承していくために、六郷工科高校と企業の挑戦は、この先も続く。



 ●会社情報
三櫻製作所
東京都大田区西六郷2丁目29−11
電話番号03-5714-4866
●会社情報
三櫻製作所
東京都大田区西六郷2丁目29−11
電話番号03-5714-4866