


 「この会社は祖父が設立したもので、生まれてから常に会社が身近な存在でした。大学卒業後に一度は他の会社に勤めていましたが、ハタノシステムに勤めることも自然な成り行きでした。入社した時の社長が私の伯母で、JCは勧められて入会したのがきっかけ」
と語るように、創業オーナーではないのだ。穿った見方をすると、二代目三代目社長という事業の基盤が既に整っている方達でないと会員としての活動は務まらない集いなのではないかと思える。この点波多野理事長は言う。
「そういったイメージを持たれる方が多いのですが、実際の会員の方には、創業社長の方や士業の先生方、個人事業主の方も数多いです。経営層ではない方もいますし、東京JCという組織は外から思われるよりはずっと多様性ある集団なんですよ」と。
実際に取材に同席頂いた東京JC側の会員の方には士業の先生などもいた。
でも、忙しくなくはない活動に勤しむ理由、もっと直言すれば、それだけ皆が集まるメリットが何かあるはずで、それは何なのだろう。この点を探りたくなり、波多野理事長が活動にのめり込んでいった過程にヒントがあるのではと考え、具にお聞きした。
「この会社は祖父が設立したもので、生まれてから常に会社が身近な存在でした。大学卒業後に一度は他の会社に勤めていましたが、ハタノシステムに勤めることも自然な成り行きでした。入社した時の社長が私の伯母で、JCは勧められて入会したのがきっかけ」
と語るように、創業オーナーではないのだ。穿った見方をすると、二代目三代目社長という事業の基盤が既に整っている方達でないと会員としての活動は務まらない集いなのではないかと思える。この点波多野理事長は言う。
「そういったイメージを持たれる方が多いのですが、実際の会員の方には、創業社長の方や士業の先生方、個人事業主の方も数多いです。経営層ではない方もいますし、東京JCという組織は外から思われるよりはずっと多様性ある集団なんですよ」と。
実際に取材に同席頂いた東京JC側の会員の方には士業の先生などもいた。
でも、忙しくなくはない活動に勤しむ理由、もっと直言すれば、それだけ皆が集まるメリットが何かあるはずで、それは何なのだろう。この点を探りたくなり、波多野理事長が活動にのめり込んでいった過程にヒントがあるのではと考え、具にお聞きした。

 波多野 和の心とは「相手を慮り調和する心」と定義しています。日本人一人ひとりの美徳の中にこの和の心が息づいていると思います。集団としての秩序、礼節や心を込めたおもてなし、これらの美徳は、すべて和の心が根底にあるからこそ、自然に表れる私たちの普遍的な価値観です。
この日本の良さである和の心を今一度世界に広めていく必要があると感じています。
世界における私たちの最大の個性は日本人であること。これだけ世界情勢や社会全体が歪んでいる今だからこそ、和の心が世界全体を恒久的な世界平和へ導く鍵となるはずなのです。
私は和の心にはそれだけのポテンシャルがあると思っています。私たち日本人は日本人としてのアイデンティティと国際社会の一員としてのアイデンティティを持ち合わせた「真の国際人」となっていくべきだと私は考えています。
―美徳溢れる国際都市「東京」とは?
東京オリンピックが差し迫った中で、私たち一人ひとりが日本人としての自覚と誇りを持ち国際人になると同時に、都市としても多様性と調和の重要性を認識し、新たな価値を生み出していく場所へと成長させていく必要性を感じて定めたものです。
私たち東京JCではこの「美徳溢れる国際都市東京」の実現のために、3つのテーマに取り組んでいます。
一つ目が「和の心を世界へ発信する真の国際人の育成」というものでして、これは実はJCIの会員たちと接する中で感じたことなのですが、彼らは教養を非常に重要視しています。私たち日本人以上に日本のことに詳しい人も多くいます。会話の中でこちらの教養を計りながら付き合うに足る人間かを品定めしているところもあるのではないかと思うこともありました。
日本人はそういったことには疎いので、日本の将来を担っていく私たち青年が意識して変わっていかなくてはと思います。世界の目が日本に向けられている今だからこそ、まずは東京JCのメンバー自らが、リーダーとして地域と世界をつなぐ先駆者となり、東京の価値を創造していくべきと考えています。
―2つ目の「多様な個性を組織の強みに変えるダイバーシティマネジメントの推進」とは?
これは、子供のころから身近に異文化がある欧米では、自ずと多様性を受け入れる素養が育ちますが、日本ではそうはいきません。「空気を読む」文化は平時にはプラスに作用するかもしれません。
ただ、組織が困難な課題に立ち向かう時にはマイナスに作用するのではないでしょうか。喧々諤々の意見が飛び交う、かえって居心地の悪い組織であるほど困難な目標を達成できる。異なる意見がぶつかり合うのをリーダーがまとめ、引っ張っていくからこそイノベーションは生まれます。
これからの東京JCを想えば、今この段階で素地を作っていく必要性を感じています。JCは一人ひとりの会員が『リーダーになるための塾』という要素も兼ね備えていますので。JCが展開している数々の社会奉仕即ち運動の中で高い目標を達成し人間力を高めること。それができるのもJCの大きな魅力ですから。
―3つ目の「東京JCブランドの確立による新たな価値の創造」とは?
JCブランドの確立が求められています。多くの人にJC活動の意義を理解してもらいたい。これだけ世界的に広がっていて、且つ多くの意義ある活動をしていますが、国内での知名度は高いとは言えません。
本会は68年間行政・団体と共に様々な運動をつくり出すと共に、多くのリーダーを輩出してきました。
現在は約650人の会員が在籍しております。これだけの歴史と人的ネットワークがあれば、社会にインパクトを与える多くの運動を行うことができると考えています。
入会資格としては25歳から37歳としているので、青年世代が集まっているのも特長です。多様な青年世代が交流することで新しいコラボが生まれてくる可能性もあると思います。
実際に今年の上半期には都議選に力を注いで、大学生たちと『主権意識と市民リテラシーの向上』を掲げて、公開討論会や政治家との懇談会などの運動を企画・実行しました。今まで政治に興味がなかったという人にも参加していただけたのは、大きな成果だったと思います。
―理事長は東京JCを政策提言のできる団体にしていきたいのか?
私たちは一人ひとりがオピニオンリーダーです。例えば今、政府が推進している働き方改革ですが、どうしても大企業側の視点で考えられていて、中小企業の考えとは隔たりがあります。それをムリに進めても中小企業の経営者が理解し活用できるようにはなりません。
そういう点では経営者や社員の教育そのものも変えていかなければならない。制度が整っても意識が変わらなければ意味がないからです。そういう問題を私たちのような団体が提言して、「政策提言」と「運動推進」という両輪でいかなければならないとは思っています。
波多野 和の心とは「相手を慮り調和する心」と定義しています。日本人一人ひとりの美徳の中にこの和の心が息づいていると思います。集団としての秩序、礼節や心を込めたおもてなし、これらの美徳は、すべて和の心が根底にあるからこそ、自然に表れる私たちの普遍的な価値観です。
この日本の良さである和の心を今一度世界に広めていく必要があると感じています。
世界における私たちの最大の個性は日本人であること。これだけ世界情勢や社会全体が歪んでいる今だからこそ、和の心が世界全体を恒久的な世界平和へ導く鍵となるはずなのです。
私は和の心にはそれだけのポテンシャルがあると思っています。私たち日本人は日本人としてのアイデンティティと国際社会の一員としてのアイデンティティを持ち合わせた「真の国際人」となっていくべきだと私は考えています。
―美徳溢れる国際都市「東京」とは?
東京オリンピックが差し迫った中で、私たち一人ひとりが日本人としての自覚と誇りを持ち国際人になると同時に、都市としても多様性と調和の重要性を認識し、新たな価値を生み出していく場所へと成長させていく必要性を感じて定めたものです。
私たち東京JCではこの「美徳溢れる国際都市東京」の実現のために、3つのテーマに取り組んでいます。
一つ目が「和の心を世界へ発信する真の国際人の育成」というものでして、これは実はJCIの会員たちと接する中で感じたことなのですが、彼らは教養を非常に重要視しています。私たち日本人以上に日本のことに詳しい人も多くいます。会話の中でこちらの教養を計りながら付き合うに足る人間かを品定めしているところもあるのではないかと思うこともありました。
日本人はそういったことには疎いので、日本の将来を担っていく私たち青年が意識して変わっていかなくてはと思います。世界の目が日本に向けられている今だからこそ、まずは東京JCのメンバー自らが、リーダーとして地域と世界をつなぐ先駆者となり、東京の価値を創造していくべきと考えています。
―2つ目の「多様な個性を組織の強みに変えるダイバーシティマネジメントの推進」とは?
これは、子供のころから身近に異文化がある欧米では、自ずと多様性を受け入れる素養が育ちますが、日本ではそうはいきません。「空気を読む」文化は平時にはプラスに作用するかもしれません。
ただ、組織が困難な課題に立ち向かう時にはマイナスに作用するのではないでしょうか。喧々諤々の意見が飛び交う、かえって居心地の悪い組織であるほど困難な目標を達成できる。異なる意見がぶつかり合うのをリーダーがまとめ、引っ張っていくからこそイノベーションは生まれます。
これからの東京JCを想えば、今この段階で素地を作っていく必要性を感じています。JCは一人ひとりの会員が『リーダーになるための塾』という要素も兼ね備えていますので。JCが展開している数々の社会奉仕即ち運動の中で高い目標を達成し人間力を高めること。それができるのもJCの大きな魅力ですから。
―3つ目の「東京JCブランドの確立による新たな価値の創造」とは?
JCブランドの確立が求められています。多くの人にJC活動の意義を理解してもらいたい。これだけ世界的に広がっていて、且つ多くの意義ある活動をしていますが、国内での知名度は高いとは言えません。
本会は68年間行政・団体と共に様々な運動をつくり出すと共に、多くのリーダーを輩出してきました。
現在は約650人の会員が在籍しております。これだけの歴史と人的ネットワークがあれば、社会にインパクトを与える多くの運動を行うことができると考えています。
入会資格としては25歳から37歳としているので、青年世代が集まっているのも特長です。多様な青年世代が交流することで新しいコラボが生まれてくる可能性もあると思います。
実際に今年の上半期には都議選に力を注いで、大学生たちと『主権意識と市民リテラシーの向上』を掲げて、公開討論会や政治家との懇談会などの運動を企画・実行しました。今まで政治に興味がなかったという人にも参加していただけたのは、大きな成果だったと思います。
―理事長は東京JCを政策提言のできる団体にしていきたいのか?
私たちは一人ひとりがオピニオンリーダーです。例えば今、政府が推進している働き方改革ですが、どうしても大企業側の視点で考えられていて、中小企業の考えとは隔たりがあります。それをムリに進めても中小企業の経営者が理解し活用できるようにはなりません。
そういう点では経営者や社員の教育そのものも変えていかなければならない。制度が整っても意識が変わらなければ意味がないからです。そういう問題を私たちのような団体が提言して、「政策提言」と「運動推進」という両輪でいかなければならないとは思っています。

 波多野理事長に、理事長としての使命は何でしょうと尋ねると、長い沈黙を経て次の言葉が出てきた。
「希望を与えること、だと考えています。希望とは人が行動を起こしたくなるビジョンを掲げること、使命感やモチベーションを生み出していくということも含めてです。
私が理事長になったのは、これからさらにめまぐるしく変化する世界において、日本人が取り入れていくべきこと、日本人が絶対に失ってはいけないことを海外での経験を踏まえて考えたのがきっかけです。
JCIのミッションは「若者たちがポジティブチェンジを生み出す成長の機会を提供すること」であります。
『百聞は一体験に如かず』、自分で体験したことに勝るものはない。自分の実体験を頭の中で咀嚼し、そこから生み出された考えや言葉だからこそ人は動いてくれる。だからリーダーたちはそれを伝えるために全力で考え、行動していかないといけない」
そういう力を育てていくためにJCがあるんだと思います、と波多野理事長は強く語る。
その言葉の底には、東京JCが戦後間もない頃に設立されてから今日に至るまで連綿と紡いできたJC会員たるものとしての矜持が見えた。聞けば、JCIへの加盟は命がけの旅を伴うものだったという。
「1949年、当時日本政府はまだ国際社会への復帰が認められていなかったので、メンバーは当時国交が途絶えていたハワイを経由して、その年の世界大会が開かれていたカナダのモントリオールに乗り込んで行きました。戦争の影響が色濃い時期でしたから道中は苦難の連続だったそうです。それでも世界大会で日本JCの存在をアピールし、JCIに加盟させてもらいたいと訴えに行きました。
しかし、そこで待っていたのは敗戦国日本に対する各国メンバーの冷たい視線でした。途方に暮れていた日本JCメンバーに、当時のラモン・デル・ロザリオ会頭が、『JCには国境も民族もない。それは、全世界の青年のものである。その誇りにおいて、われわれは今ここにかつての敵国日本のJC代表団を心からなる歓迎をもって迎えようとする。』と言った後、スタンディングオベーションにて歓迎され、JCI加盟を快諾してくれたそうです。
ロザリオ会頭は戦時中に日本とアメリカとの戦場にされたフィリピンの出身にもかかわらず、日本人の青年たちを受けいれてくれたのです。ですから私は、日本人としての誇りと同時に、JCIの一員として国際社会の一員としての活動できることを誇りに思っています」
国際人として、そして女性として。波多野理事長の抱く目標は、更なる高みにある。
波多野理事長に、理事長としての使命は何でしょうと尋ねると、長い沈黙を経て次の言葉が出てきた。
「希望を与えること、だと考えています。希望とは人が行動を起こしたくなるビジョンを掲げること、使命感やモチベーションを生み出していくということも含めてです。
私が理事長になったのは、これからさらにめまぐるしく変化する世界において、日本人が取り入れていくべきこと、日本人が絶対に失ってはいけないことを海外での経験を踏まえて考えたのがきっかけです。
JCIのミッションは「若者たちがポジティブチェンジを生み出す成長の機会を提供すること」であります。
『百聞は一体験に如かず』、自分で体験したことに勝るものはない。自分の実体験を頭の中で咀嚼し、そこから生み出された考えや言葉だからこそ人は動いてくれる。だからリーダーたちはそれを伝えるために全力で考え、行動していかないといけない」
そういう力を育てていくためにJCがあるんだと思います、と波多野理事長は強く語る。
その言葉の底には、東京JCが戦後間もない頃に設立されてから今日に至るまで連綿と紡いできたJC会員たるものとしての矜持が見えた。聞けば、JCIへの加盟は命がけの旅を伴うものだったという。
「1949年、当時日本政府はまだ国際社会への復帰が認められていなかったので、メンバーは当時国交が途絶えていたハワイを経由して、その年の世界大会が開かれていたカナダのモントリオールに乗り込んで行きました。戦争の影響が色濃い時期でしたから道中は苦難の連続だったそうです。それでも世界大会で日本JCの存在をアピールし、JCIに加盟させてもらいたいと訴えに行きました。
しかし、そこで待っていたのは敗戦国日本に対する各国メンバーの冷たい視線でした。途方に暮れていた日本JCメンバーに、当時のラモン・デル・ロザリオ会頭が、『JCには国境も民族もない。それは、全世界の青年のものである。その誇りにおいて、われわれは今ここにかつての敵国日本のJC代表団を心からなる歓迎をもって迎えようとする。』と言った後、スタンディングオベーションにて歓迎され、JCI加盟を快諾してくれたそうです。
ロザリオ会頭は戦時中に日本とアメリカとの戦場にされたフィリピンの出身にもかかわらず、日本人の青年たちを受けいれてくれたのです。ですから私は、日本人としての誇りと同時に、JCIの一員として国際社会の一員としての活動できることを誇りに思っています」
国際人として、そして女性として。波多野理事長の抱く目標は、更なる高みにある。
◇

が、六本木ヒルズアリーナで開催
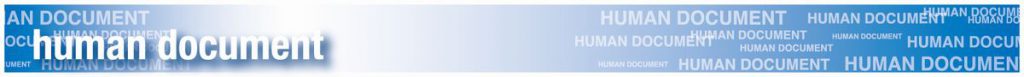

お話を伺った応接室には、歴代理事長の写真が。
TOPページ