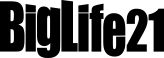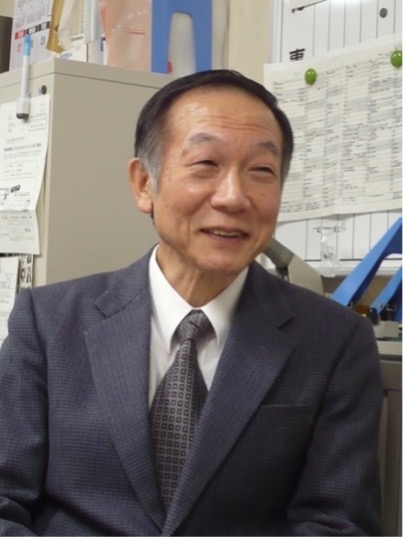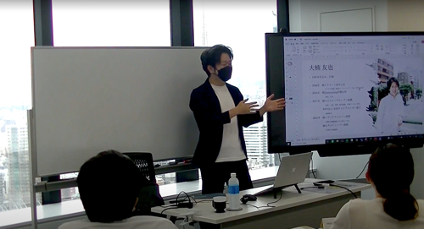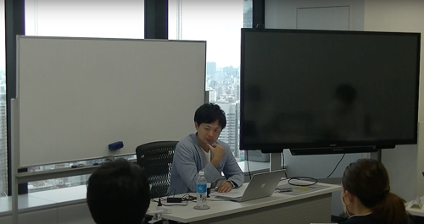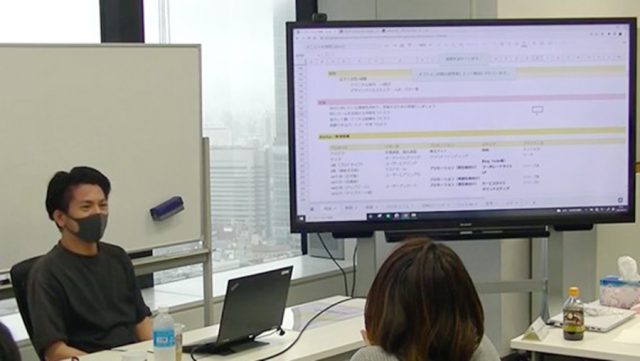100年経営研究機構 後藤代表理事×藤村専務理事 特別対談〜今こそ学ぶべき、長寿企業が実践してきた経営の本質〜

写真左から 藤村雄志氏 / 後藤俊夫先生
昨今、急変する社会情勢や金融資本主義の行き過ぎにより、あらゆる側面で社会のサステナビリティ(持続可能性)に軋みが生じるようになった。
かように劇的に変化する外部環境を前にして、経営のかじ取りを担う経営者には確かな知恵や胆識が求められるわけだが、巷間、企業の寿命には30年説を始め諸説が言われてきたものが近年はそこで挙げられる数字の加減が、「10年だ」「5年だ」となお一層の薄命となっていることにもこの環境の激烈さが現れていると言えるのではないか。
一方で、日本は100年以上の長寿企業数が世界一と言われる長寿企業大国だという事実をご存じだろうか。
ここになぜ日本が長寿企業大国となったのか、また長寿企業を長寿たらしめる要諦は何なのか、その謎を詳らかにする100年経営研究機構という団体が存在する。
今企画は、同機構の後藤代表理事と藤村専務理事の対談を通じて長寿企業大国日本の秘密を紐解いていく。
100年経営という手段

藤村雄志 情報を中小企業の経営者の方にとってよりわかりやすく、かつ届きやすくするために、アカデミックな部分を実学的にする方法を模索して形になったのが、100年経営研究機構なのです。
藤村雄志(以下、藤村):100年経営研究機構はその名のとおり、100年以上続く長寿企業大国を生み出した日本の風土や特殊性を尊び、その智慧と教訓を次世代に伝えていくことを目的に活動しています。
なぜ、今100年経営を学ぶのかと言えば、経営者の方々からは「会社なんて長く続かなくても、役割を終えたら終わったっていいじゃないか」、経済学者からは「一定の新陳代謝は必要でもあるのに、なぜ100年経営にこだわるのか」という指摘を受けることがあります。これについては、自分の中でも反芻しておりまして。物事には目的と手段があるという話がわかりやすいかと思います。
100年経営を学ぶ、あるいは目指すことだけが目的化してしまうとこれは確かによろしくない。あくまで手段として100年経営を目指すことがポイントであることは間違いありません。企業活動をしてきて、結果的に100年経営になっているという企業は良い経営をしてきたということになるのではないか。
そういった企業から企業の在り方や経営の本質を学べるところがあるのでは、と考えています。こういった点がこれまであまりにも軽んじられてきたのが、昨今の金融資本主義の流れだと考えています。
一方で、ここ近年はこの点に多くの方が危機感を覚え、企業の公器性とは何なのか、永続させるためにはどうすればよいのかを考えたいという切実な想いが、社会のいたるところで醸成されていることを強く感じます。このあたり後藤先生はどう思われますか。
いくら大きい会社でも、長く続いている会社でも、潰れるときは潰れる
後藤俊夫(以下、後藤):100年経営を学ぶ目的を説明するために、私が長寿企業の研究を始めた経緯からお話しましょう。私は1966年にNECに入社して33年の間、営業、事業戦略、マーケティングに携わってきました。その頃経験したことの中に、今いただいた質問に対する答えがあります。
NEC自体が1899年に創業された100年経営企業だったのですが、あるとき上司から言われた言葉を今でもよく覚えています。「いくら大きい会社でも、長く続いている会社でも、潰れるときは潰れるんだ」という話でした。我々の時代は普通、勤めたら一生その会社にいるという考えが当たり前の時代でした。会社は永遠に続くと思っていました。でもそれは違うと上司から言われ、NECのように100年以上続いている企業ですら潰れる可能性があるのは、なぜなのだろうと思いました。
もう1つきっかけとなったのは、1984年に日経から出た『会社の寿命―“盛者必衰の理”』という本です。当時の企業人は読んだ方が多いのではないでしょうか。本の中では、「会社の寿命は30年」だと語られています。実は、後に理論的に誤りが指摘されていますが、いずれにしても企業の寿命は永遠ではないと言っていることは正しいです。そうするとまた、なぜだろうという疑問が湧きました。ここまでは、すべて現場にいた人間としての話です。
1999年に33年間勤めたNECを少し早めに退職し、大学に移りました。そのときに研究テーマを選ぶ決断を迫られ、いくつかの偶然の要素が重なり、長寿企業研究を選んだのです。私が選んだテーマは、当時世の中で注目する人が少なく、学者仲間には「なぜそんなことをやるんだ」と言う人もいました。研究を初めてから約20年が経った今、やっと日の目を見ることができたように思います。
なぜ長く続く企業と続かない企業があるのか。その違いは何か。そもそも日本に100年続く企業がどれくらいあるのか。当時はこれらの問いに答えてくれる人が誰もいなかったので、自分で1つ1つ調べ始めたのが始まりです。調べてみた結果、日本だけで約25,000社も100年経営企業があることがわかりました。これは、私自身全く想定していなかった数字でした。
地道に調べ続けた、唯一無二のデータ
藤村:よく言われることですが、当時、帝国データバンクや商工リサーチのような調査会社にデータはなかったのでしょうか?
後藤:もちろんありました。ただ、当時は対外的に発表されていませんでした。また、我々としても、調査会社からデータがもらえるとも考えていませんでした。彼ら自身も、当時はそのようなデータに強い関心や商品価値を見ていなかったのではないでしょうか。
藤村:調査会社などが持っているデータと後藤先生のデータは、細部で見ると性質が異なりますよね。調査会社は性質上、売上がいくら、利益がいくらといった、ある意味定量的なデータの集積といった趣が強いと思います。一方、後藤先生のデータは家憲の内容や、何代目であるかといったことも含めて1つ1つ調べた定性的なデータとなっている点が特長です。我々としては、こうした、世界でオンリーワンの定性的なデータという点に価値があると見ています。
家の繋がりを重要視する日本文化
後藤:そうですね。文字通り、日本は世界トップの長寿企業大国です。100年以上継続する企業数ランキングにおいて、第2位のアメリカが11,735件なのに対し、日本は25,321件と倍以上の差をつけています。ちなみに、200年以上継続企業数は日本が3,937件で1位、ドイツが1,850件で2位となっています(2014年現在、出典100年経営研究機構)。
すると当然、なぜ日本は長寿企業大国なのかという疑問が出てきます。これはよく聞かれるのですが、あと5年、10年待っていただきたいと冗談半分で答えています。それぞれの国には固有の歴史や社会制度があります。研究者としてはそれらをつぶさに比べる必要があるので、簡単に答えを出してはいけないと考えているのです。
日本と世界の比較の際、経営者の多くは経営方法やテクニックの違いの話をされます。確かにその違いもあります。例えば日本でいうと、養子という仕組みが割りと珍しくありません。具体的な企業としては、スズキ自動車が挙げられます。
創業者は鈴木さんですが、2代目、3代目、4代目は、実は皆さん養子なのです。このような養子の話をすると、海外の方からは信じられないという反応が返ってきます。なぜかというと、国によって歴史や家の仕組みが違うからです。
この点を説明するには、そもそも家とは何か、という話になります。中国との比較がしやすいのですが、中国は純血主義で血が繋がっていることを極めて重要だと考えています。ところが日本では、特に江戸時代、武士が家を継ぐということが極めて重要でした。「お家断絶」という言葉がよく時代劇にでてきますが、後継者がいないために家が取り潰されてしまうということを指しますよね。潰されてはならない、何とか家を続けなくてはというときに生まれたのが、養子です。
武士の中でこのような動きがあると、やがて商人がまねをしました。自然と商人も家を継ぐということに必死になってゆくのです。こうして日本では家を繋げるための仕組みとして、家の外から養子を取り入れていきました。
重要なことは経営学の外にある
藤村:なるほど。かの有名な民俗学者である柳田国男は、日本人は家筋を重視すると捉えました。中国人やユダヤ人は血の繋がりである血筋を大事にするけれど、日本人が重要視するのはずっと一緒にいたという事実性、近接性(プロクシミティ)を重視するのだと。この近接性の話が家の考え方や企業の存続にも繋がるものがありそうですね。
後藤:今おっしゃった柳田国男や、他に和辻哲郎なども非常に密接な関係があります。経営者の方は経営という観点で見がちですが、それはあくまで全体の中の一部分の話です。今お話ししているように、家族や歴史、封建社会を見ていくときには民俗学、社会学、家族学が極めて重要になります。経営学の外に知るべきことがたくさんあるのです。
もっと重要な要素として、商業倫理や哲学が非常に重要です。例えば儒教や仏教、そして神道。さらに、欧米との比較のためにはキリスト教の知識も必要になってきます。研究を進める中でようやくわかったのですが、長寿企業の学問というのは非常に総合的な学問なのです。

後藤俊夫 振り返ってみると、2007年6月の「NHKスペシャル」という番組がきっかけで、自分の頭の中でこのような意識が出てきたのだと思います。実は、最初に日本が長寿企業大国であるということを言ったのは私ではありません。NHKが1時間番組で私のデータを取り上げ、「長寿企業大国にっぽん」という言葉を使ってくれたのです。国際比較がなければ、「大国」と言えませんよね。日本のことを把握した上で国際比較をしたということになります。このことによって、日本が世界で稀に見る長寿企業大国だということがわかったのです。
自然災害と戦ってきた日本の歴史
藤村:ただ、研究に対して海外から過去に批判が出てきたことがありましたよね。
後藤:ええ、海外の学者から見れば、日本に長寿企業が多いのは当たり前だという指摘です。日本は島国だから海外からの侵略がなかった。さらに、内乱も少なかった。それ故に、日本では企業経営が長く続くのが当たり前だという批判があります。
藤村:その批判に対して、後藤先生はどういったご意見をお持ちなのでしょうか。
後藤:私の答えとしては、50%賛成で50%反対というものです。島国というのは事実ですし、海外からの侵略は元寇のときくらいしかありませんから。内乱も応仁の乱や明治維新があったけれども、ヨーロッパや中国とは比較にならないくらい少なかったのです。
けれども、日本には台風や地震といった自然との戦いが毎年のようにあります。津波は60年に1回くらいでしょうか。3.11以降、このことを言うと皆さん受け止めてくれますね。自然災害が起こるとどうなるかというと、3.11のときにわかりましたが、会社も工場も全て流され、多数の人々が尊い命を失ってしまいます。
100年以上続いている企業には、大きなチャレンジが4つ指摘されます。1つは政治的な体制が変わること。例えば明治維新や第二次大戦の敗戦が挙げられます。2つ目に、自然災害。3つ目に、家族の中における事業承継のリスク。日本も海外も同じですが、日本はお家を継ぐことが非常に大事だということで、様々な工夫を取り入れてきました。4つ目は、事業分野に特有な大きな変革があります。産業革命は何度も起こり、IOTのような技術の変革と共に規制の変化もありました。
こうして大きく4つのチャレンジがあり、その中で見ると自然災害は非常に大きな要素の1つなのです。そういう意味で、50%賛成で50%反対という私の答えに、最近は皆さん納得してくれます。
伝統とは、変化を続けること
藤村:生物学では変化できるもの、環境に順応できるものが強いとされます。100年企業というと、頑なにカタチを変えずに事業を継続し続けていると思われがちですが、全くもってそんなことはないんですよね。たとえば、和菓子の名店である虎屋さんは、「伝統と革新」を家訓としています。
古いものを守るだけでなく、新しいものにもチャレンジする。価値観、考え方のベースにあるスタンスが変わらないだけであって、事業を守りぬくためには変化をいとわない果敢な姿勢が、老舗企業の歩みには見てとれます。
後藤:そうですね。変化の事例はたくさんあります。1994年に『老舗企業の研究』という本を仲間と書いたのですが、その頃の私たちは「伝統と革新のバランス」を長寿企業の特徴として掲げていました。これは世間の常識とは全く逆でした。一般的には、長寿企業は古くからの伝統を守ってきたと思われていたのです。
その後、本の増補改訂として2012年に第2版を出すのですが、そのときの私たちは「伝統とは革新の連続である」という言葉を使いました。変化を続けることが伝統なのだ、というメッセージです。そうしなければ長くは続かないということが、調査が進むにつれてわかってきたのです。
ただし、革新の連続といっても長寿企業の独特な革新のやり方に着目して連続的な革新という言葉を使っています。ある日白が黒に突然なるのではなく、段々と黒さを増していってようやく黒になる、そんな連続的な変化だということです。100年企業はそのやり方が非常に上手かったと言えます。
20年先の未来の可能性
藤村:では、今後日本の人口が減っていく中で、100年企業の数はどう推移していくのでしょうか。
後藤:時間軸によって見方は変わりますが、長寿企業は確実に増えてきています。実は、日本におけるベンチャーブームの第1期は1968年の明治維新なのです。世間一般では1970年と言われていますが、もっとマクロで見たときの第一次ベンチャーブームは1868年前後の明治維新期で第2のブームは1945年、第二次世界大戦敗戦以降です。ソニーや京セラがそれにあたります。そしてようやく最近、第3のブームが始まりました。
年によりますが、日本の長寿企業は毎年1,000〜3,000社増えています。2014年時点の調査で長寿企業数は25,321社となります。2018年現在はさらにそこから数年経っているので、足し算すると3万社を超えると推定されます。
生まれる会社がある一方、潰れる会社もあります。ただし、100年以上続いている会社が潰れる比率は非常に少数です。3代以上続いていると、その生存率は高くなるのです。ですから、引き算と足し算をすると毎年結果的に企業数は増えていることになります。今から20年先を考えたとき、絶対数は増え続けるでしょう。その後どうなるかというと、日本の人口および新規起業数の推移を考慮しなければなりません。
ただ、日本の人口がいずれ5,000万人になるという説がありますが、それは外れるのではないかと私は考えています。人口学の理論によれば人口の予測が高確率で当たるのはこの先20年間に限定されているのです。2040年、2050年と20年を超えた未来に人口が5,000万人になるとは、予測できません。
なぜかというと、政策的に様々な取り組みが進むと子どもを産みたいという人が増えてくると考えられるからです。フランスがその例です。我々が子どもの頃は、フランスでは今の日本のように少子化が深刻でした。しかし、フランスは真剣に対策に取り組んだ結果、人口増加に変わったのです。5年や10年では政策の成果は出ません。日本でも既に児童手当や男女機会均等など、様々な政策がありますよね。ですから、20年先の未来は今とは異なる環境になっている可能性が十分に考えられるのです。
身の丈経営が無駄をなくす
藤村:100年経営を学ぶ意義とは何なのでしょうか?
後藤:結局、企業において最も重要なものは何なのかという話になります。ゴーイングコンサーン(継続企業)という言葉がありますよね。つまり、企業は存続することが当然とされているということです。例えば、会計学はそれを前提としてでできています。減価償却という概念にも同じことが言えますね。
我々は企業で働いている人間ですが、一方で消費者でもあります。消費者が商品を買うときに、製造会社が明日倒産するとは想定しませんよね。もし商品が壊れれば、保証サービスの継続を前提としています。ステークホルダーは企業が存続することを前提としており、会計学でも前提としている。存続することは、極めて重要であるということです。
もう1つは、地球環境の保護という観点です。私は、2014年に2007年ノーベル平和賞の受賞者であるアル・ゴアさん(元米国副大統領)にお会いした機会に強く主張したのです。ゴアさんの『不都合な真実』という著書と私の考えを結びつけたところ、完全に彼と意見が一致したのです。
実は、100年続く経営のやり方というのは身の丈経営、つまり無理のない経営だと言えます。身の丈経営という言葉は、自分の身の丈に合わせて、あるいは自分の資源の範囲内で経営をするということです。無理をしない経営ですから、その分リスクが少ない。それに対して、私が33年間在籍していたNECのような大企業では、短期決戦でリスクが大きくアップダウンも激しいという、全く反対のものでした。
アップダウンが激しい経営と少ない経営の違いは、特別損失が多いか少ないが、一つの指標として見て取れる。
例えば、人材についてみると、景気がいいときは大量に採るために採用費用が必要になります。一方、経営が傾いたときはリストラといって、人を放出します。早期退職にも費用がかかります。つまり、短期決戦の企業は余計なお金をかけて人を確保し、それにも関わらずまた余計なお金をかけて人を放出することになります。設備投資でも同じことが言えますね。ヒト・モノ・カネの全てに渡って、短期決戦のやり方の多くは事業の拡大局面と縮小局面の両方で無駄が多いのです。地球上の資源は有限です。企業として、経営の基本のところでその点を意識しているかいないかが重要なのです。この話にゴアさんは大変合意してくれました。
藤村:ゴアさんの話で言うと、今年創業1300年を迎える金沢の法師旅館(718年創業)の話に通ずるものがあります。
毎年100年経営研究機構として、旅館に視察に行かせてもらっているのですが、46代目の法師善五郎さんに講義をしてもらったときのことです。恥ずかしながら、「君たち、パリ協定の動向にもっと注目しなさい」というお言葉をいただきました。法師さんがおっしゃるには、法師旅館がこれだけ長く続いているのは地球の環境が成り立っているからである、と。この関心と意識は素晴らしいですよね。
本当に長く続いている企業というのは、自分が存在しているのはお陰様だという意識を深くお持ちなのだと。お客様、社員、取引先、社会、地球のお陰という感覚で生きていらっしゃる。いきなり金沢の旅館の経営者から「パリ協定」という言葉が出たのは、こういうことなのかと合点がいき、非常に新鮮でした。
今学ぶべきは、三方良しのビジネスモデル
後藤:2017年2月22日に、2006年ノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌス博士に会いました。彼は、ソーシャルビジネスが重要であると指摘していました。今の若い方はソーシャルビジネスに非常に理解がありますよね。彼の言うソーシャルビジネスには7つの原則があって、要約すると事業性と社会性の両立となります。それこそまさに、長寿企業が取り組み続けてきたことなのです。
自分の私利私欲のためでは、企業は長くは続きません。一方で、ビジネスですから慈善事業でもありません。その両立が必要なのです。古くから、日本の企業は三方良しの考えでやってきました。21世紀の今においてこそ、過去を単に懐かしむのではなく、我々のビジネスモデルはどうあるべきかと考えたときに1番いいモデルが、ここにあるのです。
藤村:ありがとうございました。

<対象者プロフィール>
後藤俊夫(ごとう・としお)
一般社団法人100年経営研究機構 代表理事
日本経済大学大学院 特任教授
1942年生まれ。東京大学経済学部卒。大学卒業後に日本電気株式会社 (NEC Corporation)に入社し、1974年ハーバード大学ビジネススクールにてMBAを取得。1999年静岡産業大学国際情報学部教授、2005年光産業創成大学院大学統合エンジニアリング分野教授を経て、2011年より日本経済大学渋谷キャンパス教授に就任。同経営学部長を経て、2016年4月から現職に就く。日本における長寿企業やファミリービジネス研究の第一人者であり、精力的に教育活動や講演・セミナーなどを行っている。
藤村雄志(ふじむら・ゆうじ)
一般社団法人100年経営研究機構 専務理事 兼 事務局長
株式会社VALCREATION 代表取締役
1978年生まれ。山口県出身。同志社大学商学部卒。大学卒業後、株式会社ベンチャー・リンクに入社。その後2004年に起業し、これまでに30社以上の事業支援プロデュースを行ってきた。2011年、株式会社VALCREATION設立、代表取締役就任。2015年、一般社団法人100年経営研究機構設立、事務局長に就任。教育機会の創造を通じ次世代リーダーの育成に情熱を注いでいる。
<会社情報>
一般社団法人100年経営研究機構
設立:2015年9月9日
住所:〒150-0001東京都渋谷区神宮前 6-19-17 ペリエ神宮前5 VALCREATION内
TEL:03-5778-3228
URL:http://100-keiei.org/