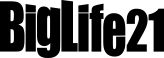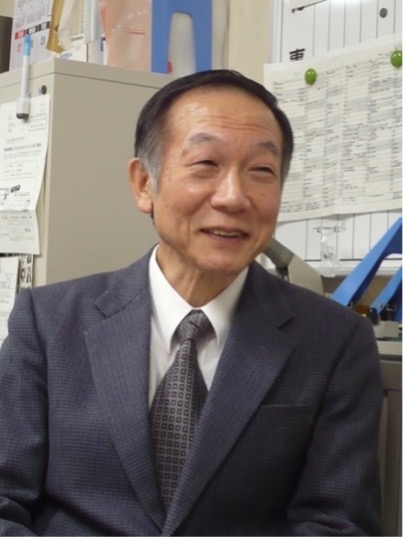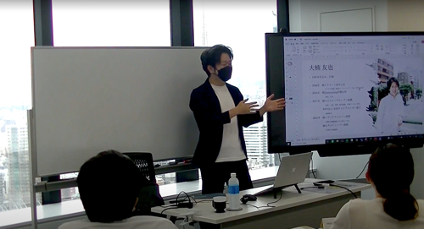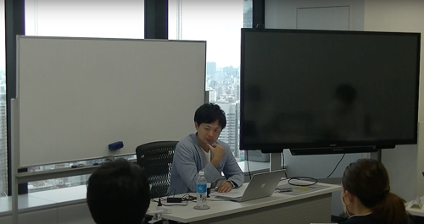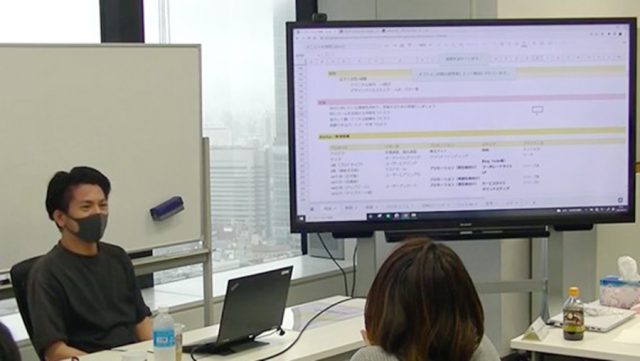これからの日本の技術経営への問題提起 株式会社日立メディコ元社長 三木一克氏

2010年頃から世界的に株主資本主義による企業の短期業績を偏重した、ショートターミズムの修正がはじまり、企業は中長期的にステークホルダー全体への価値創造をしていくべきものと評価基準が変わろうとしている。もともと企業の技術開発には時間がかかることから、この傾向は好ましいと言えるが、それにしても長期ビジョンはどうであれ、中期経営計画のコミットメントとなると、3~5年の間に成果を出さねばならないということになる。
また、中小企業の技術マネジメントからすれば、今の収益につながるものか、それとも将来の利益体質確保かといった二律背反の課題が横たわる。このように製造業が求められる業績上の成果と技術マネジメントの相克といった問題に、日本企業はこれからどう対処し、本物の技術開発を行っていけばよいのか?
技術経営の視点から見たときにあるべき方向性について株式会社日立メディコ元代表執行役社長の三木一克氏にお話を伺った。
資本主義市場からの業績への要請と本物の技術開発への取り組みといった観点からのジレンマ
日本の技術経営云々と言う前に、三木氏が属していた日立グループの技術開発環境を概観してみよう。激しかったリーマンショックの爪痕が残る2009年3月期、日立製作所は、日本の製造業として過去最大となる7873億円の赤字を計上した。
「日立が巨額の赤字を出した時、赤字の原因を抜本的に無くそうということで、構造改革に踏み切りました。薄型テレビ事業からの撤退 、自動車機器関連事業の再建、HDD事業の売却。そして社会の問題解決を技術によって実現する、社会イノベーション事業へと舵を切りました」
日立の社会イノベーション事業とは、「制御・運用技術であるOT(Operational Technology)とIT、プロダクト・システムを組み合わせたトータルソリューションを提供し、社会やお客さまが直面しているさまざまな課題を解決」するというものだ。
この取り組みは、技術志向からマーケティング志向に転換し、企業戦略としては至極順当なものに見えるが、三木氏に言わせれば、ここに見逃してはならない陥穽があるという。ソリューションと言った瞬間に、顧客ニーズに対応するため、顧客に合わせたカスタマイズが求められる。しかし、カスタマイズとは顧客ごとの個別仕様が求められることで、この競争に参加することが企業収益上、貢献するかと言うと必ずしもそうでもない。
もちろん、研究部門が技術研究だけしていて、必要に応じて市場ニーズに合わせて出て行くという旧来のたこ壺型では時代遅れだ。しかし、コア技術を磨いていくには20年~30年かかるが、もしその中から、他社にまねのできないダントツ技術(日立ではこのように呼んでいた)を創出できれば、価格競争にさらされることなく、収益力を確保できる。つまり、あらゆる企業がソリューションにシフトし、即効性を求める技術間の競争が起こり、コモディティ化しても、圧倒的な基礎技術力があれば競争力を保持できるのだ。
「ただ、現状では、技術開発のほうが経営陣の任期より長いとすると、資本市場の圧力と闘わねば本物の技術は守れません。成果をできるだけ早く求める風潮となって、ソリューション、というとどうしても今の顕在化している顧客の要請にどう対応するかという話になってしまう。経営陣はその葛藤の中で技術開発を進めていかなければなりません」と三木氏は指摘する。
画期的な技術を生み出す日立の研究例~ひずみセンサの開発
三木氏は32年間日立の研究開発部門に所属し、その後9年間、日立メディコの経営陣として日立グループの医療機器事業に関わった。
「まず私が日立に入社を決めた経緯をお話しましょう。最初の配属先の原子力研究所(後のエネルギー研究所)は中央研究所の王禅寺支所としてスタートしました。その当時の所長は谷口薫さんという方です。谷口さんは、京都から就職活動で出てきた、たった1人の学生のために、研究所を丸一日かけて案内してくれたのです。
各部門の責任者たちの話を聞いて回ると、全員がことごとく独創的で新しい技術研究を行っている自負と、情熱に満ち満ちていました。この研究所のチャレンジングな組織風土と自由闊達な空気を感じ、入社を決めたのです」
その谷口氏には、技術研究、技術開発、設計、生産といった技術経営はさることながら、部下のマネジメントや人間としての振る舞いまで、人生の師と呼べるほどに多くのことを学んだという。
「さて、日立の研究活動は新入社員が入社と同時に、研修員として2年間の研究テーマを与えられます。そして研究に取り組んだ後に、テーマに関する発表会を行います。その発表会では成果というより、研究プロセスを評価します。彼でなければできなかったことは何だったのかということ。それから、その上司が、その能力をどうやって引き出していったかを見るのです。
その次の3年間で、企画員発表会というのをやります。これは、研究所のリーダーたちを前に研究成果を発表し、研究者として自立できるかどうかを判断するために行うものです。非常に緊張感があってピリピリしていて、発表まで漕ぎつけるには相当神経をすり減らします。
この3年間の成果を見ながら、技術シーズを発掘したり、研究所に向いているのか事業部に向いているのかその人の適性を判断していくのです」
発表会後に適性があれば研究者として、研究を進めていくことになるが、実際にその後製品化への成功確率はどうかというと2割5分から3割くらいなのだという。5年かけて研究しても、失敗することが7割。しかし、失敗はそれを活かす意識があれば、次に必ず生きてくる。失敗から何を学ぶかが重要だと三木氏は指摘する。
このように研修員制度からはじまり、実際に研究開発に入り、失敗を乗り越えて本物の技術が出てくるまでに、実際にはかなりの時間を要することになる。
「一例をあげると、2003年のころ、研修員発表会の中から出てきたものの中に半導体ひずみセンサというものがありました。その研修員は、機械的なひずみを加えたときに電気抵抗が変化する効果を利用した半導体ひずみセンサの試作品を出してきた。直感的にイノベーション創出の可能性が高いと判断し、すぐに指導員の太田主任研究員をリーダーにして本格的な開発に取り組むように指示したのです」
ひずみセンサは、自動車機器、産業機械、インフラ構造物などに幅広く搭載でき、物体に力が加わることによって生じるひずみなどの物理的な変化を高精度に測定することができる。これにより、機器、設備の状態を瞬時に管理でき、制御を効率化する。
つまり多様な機器の円滑な動作を可能にしたり、故障の予兆診断などに活用できる汎用型のセンサーなのだ。
三木氏は、2005年に研究所を去ることになったが、太田主任研究員に何としても開発を継続をするように指示をした。この技術はリーマンショック後の研究所の構造改革の最中、自動車関連機器の研究分野に組み込ませることができた。
そして2015年、日立オートモーティブシステム株式会社で製品化され、ようやく日の目を見ることになる。この半導体ひずみセンサの革新性、独創性、応用性が高く評価され、米国R&D Magazine社主催の2016 R&D 100 Awardsや経産省主催の2017年度「ものづくり日本大賞」の内閣総理大臣賞などを受賞した。
「時代が変わって、今やIoTがもてはやされるようになりましたが、IoTの実体は、センサーネットワークなのです。ビッグデータの重要性が声高に言われていますが、むしろデータを取り込む入口のセンサーの方も重要なのですね。この技術は2003年から研究をはじめ、12年後の2015年に花開きました。
しかし、2003年の当時はIoTの時代がくるなどとは誰も予測をしていません。しかし、結果として革新的な基礎技術はいろいろなものに利用可能になっていくものなのです」。
基礎技術を育てるまで20~30年はかかる 原子力~陽子線治療設備
「さらに原子力などの放射線に関わる基礎技術の開発は、20~30年は当たり前にかかってしまいます。たとえば原子力発電プラントでは、日立はGEとの結びつきが強いのですが、そのGEから1960年代後半に沸騰水型軽水炉(BWR)が導入されました。このBWRの中核である炉心として、エネルギー研究所の竹田練三氏が独創的な国産技術のWNS炉心を開発しました。
この炉心では、ウランの濃縮度を上部で高く、下部で低くなるように二領域にわけたことにより、定常運転時の制御棒挿入を不要とし、また定期検査期間の短縮により、稼働率の向上が可能となりました。このWNS炉心が本格的に実用化されたのが、東京電力福島第二原子力発電所で1983年の話になります」
「竹田氏はその後、核燃料のゴミ問題に対応すべく、超ウラン元素を燃やし尽くせる原子炉(TRU燃焼炉)の開発に取り組んでいます。この原子炉は、マサチューセッツ工科大学、ミシガン大学、カリフォルニア大学バークレー校と組み、その性能が確証されました。この結果をもってようやく2015年、文科省から原子力システム研究開発事業に採択されました」
炉心や原子炉の設計にあたっては、大型コンピュータによる膨大な計算が必要で、実績データで検証された多種類の設計プログラムを並行稼働して進められる。これにより同時に、基盤技術を支える計算科学の分野も発達し、様々な産業分野で数値シミュレーションを活かした、技術開発や製品開発ができるようになってきている。
東日本大震災による原発事故の後、この分野に国も研究予算を配分することが難しくなっていきている。しかし、こういった放射線の蓄積した研究があるからこそ、日立の医療機器の開発ができているのも事実なのだ。
「例えば、陽子線によるがん治療という分野があります。陽子線や炭素線などの粒子線を用いたがん治療の有効性は、医学物理の分野ではかなり前から言われてきました。陽子線治療の特長は、体の奥にある臓器の患部に合わせて、がん細胞への破壊力がピークになるように照射できることで、患部への線量を集中的に高め、周辺の健常な組織への影響を抑えることができます。
この陽子線治療が最近ようやく実現できた背景には、患部へ照射する陽子線の高精度な照射制御技術や線量計画・管理技術の進歩があるのです。この『スポットスキャニング照射技術』については、ようやく2011年に日本国内の薬事承認を受けました。
さらに、肺や肝臓など呼吸により患部が移動する臓器への照射は、放射線治療の分野において大きな課題でした。そこで、北海道大学と共同で、北海道大学が開発した腫瘍の動きを追跡する技術と、日立のスポットスキャニング照射技術を融合し、動く腫瘍にも陽子線を高精度に照射できる技術を開発しました。この技術は、2014年に北海道大学病院で世界で初めて治療に使われ、その後世界に普及しつつあります。
中小企業の技術は宝の山~繊維産業の紡織技術を生かす、繊維加工技術の開発
さて、今までの話は大企業のシステマティックな技術経営の話だったが、一方大企業では、一つの技術で1,000人以上の人的コストをまかなわねばならないなどの、大仕掛けなものが必要となってくる。逆に、小回りが利く中小企業でないとできない分野は山のようにあると三木氏は言う。

「実は、私は国立研究開発法人 科学技術振興機構の産学連携アドバイザーも務めていて、中小企業の技術に触れる機会も多いのです。中小企業で蓄積されてきた技術に、国の研究機関やベンチャーの革新的な技術が加わることで、まったく新しい世界が生まれることがあります。
例えば、産業技術総合研究所といくつかの繊維機械メーカ、繊維メーカが協力して「エレクトロスプレー繊維加工技術」が開発されました。従来、紡糸の染色は大きな浴槽に糸束を浸して乾燥する方法を採っています。開発した技術では、帯電した一本の糸にスプレーを吐き掛け、スプレーの吸着率が99.9%になるようにできるのです。つまり、一本の糸に黒、灰色、赤……といった色を付けることができ、さらに途中で配色を変えカラーグラディエーション染色ができるのです。
さらに、これに銀を吹き付ければ抗菌機能が付加できるし、導電性の糸にすれば、センサを編み込んだウェアができる。この技術を用いた生地サンプルを、イタリアの展示会ミラノウニカに出展したところ、有名なオートクチュール数社から早速サンプル生地の引き合いがあったそうです。」
この「エレクトロスプレー繊維加工技術」は、産総研の革新技術と繊維産業で長年にわたって蓄積されてきた成熟技術が融合し、圧倒的な速さで実用的な技術が実現された。この技術は、廃液をほとんど出さずクリーンかつ小型であり、オフィスなどでも使用できるため、今後、日本の伝統産業である紡績業界だけでなく、アパレル業界のデザインプロセスにも変革を及ぼすものと期待されている。
このように自社のコア技術に外部の先端技術を組み合わせて行う、中小企業ならではのオープンイノベーションを活用した、技術マネジメントは非常に可能性があると三木氏は語る。国の研究機関や大学、ベンチャーとの取り組みは、敷居の高い印象や、失敗例を聞いて躊躇しているかもしれないが現実には様々な共同開発が進んでいるのも事実なのだ。
技術経営で最も重要なものは開発者魂
技術開発は革新的なものほど、そして本質的なものほど、経営リソースも時間も使うし、株主も含め周囲の抵抗も大きい。しかし、それらを跳ね返し前に進んでいくには、大企業も中小企業も、重要なのは本源的な開発者の情熱なのだ。

「私が事業部門に異動したある日のこと、谷口さんから手紙が来ました。『エネルギー研究所をボーアがコペンハーゲンに作ったニールス・ボーア研究所のようにしたかった』と。ボーアは、アインシュタインとともに天才と呼ばれた、量子力学の育ての親ですが、ハイゼンベルクやシュレーディンガーなどの世界のノーベル賞物理学者を研究所に呼び寄せていました。
周知のとおり、この研究所が世界の物理学の拠点となって、独創的で革新的な研究成果を発信し物理学の世界を変えていきました。普段は考えていることをなかなか明かさない谷口さんの秘めたる志の内を知って、ぐっと胸が熱くなりました。
20代、30代のころにはやりたいことを自由にやらせてもらっていたわけですが、この時日立の開発者魂の火を燃やし続けなければならないと決意しました」
「結局、リーマンショック後に大きな赤字を出し、研究所は大再編、株主からも厳しい要求を突き付けられながら、グループとしての新しい技術マネジメントの在り方を模索するなか、結局、行きついたのが谷口さんの魂を揺さぶる言葉であり、さらにその源流は100年前に日立の創業者小平浪平が示した日立創業の精神そのものにあったのです。
こんなことを考えているとき、日本ではなく米国の関連会社Hitachi Data Systems Corp.が、米国西海岸の働きたい会社ランキングで分野別1位に選ばれたという話を聞き、人事のマネージャーにどのようなことをやっているのか、情報を取り寄せました。なんと、この会社は日立創業の精神を英語化して、それを企業文化の中核概念として愚直に社内での浸透を図っていたのです」
その日立の創業の精神は以下のようなことばで表現されている。
和:他人の意見を尊重しつつ、偏らないオープンな議論をし、一旦決断に至れば、共通の目標に向かって全員一致協力すること。
誠:他者に責任を転嫁せず、常に当事者意識を持って誠実にことに当たること。
開拓者精神:未知の領域に、独創的に取り組もうとすること。常に専門分野で先駆者でありたいと願い、能力を超えるような高いレベルの目標に挑戦する意欲のこと
明治政府の富国強兵政策の余波で、先進技術は何でも欧米から導入と言う思考パラダイムの中、小平浪平ひとりが、日本の工業を発展させるためには、自主技術、国産技術によって製作するようにしなくてはならない、その独創性こそが日本が発展していく道だと刮目していた。
「短い期間こういった様々な出来事もあって、技術開発者のDNAを次の世代に引き継ぐのが自分の使命と考え、これまで経験した実践的な技術マネジメントを教えようと意を決しました。そういった経緯で、日本で技術経営を啓蒙する技術経営士の会に入り、日立グループだけでなく、日本大学、東京工業大学、お茶の水女子大学で、技術マネジメント(MOT)を教えるため教壇に立つようになったのです」
日立製作所の始まりは、小平浪平が、茨城県の人里離れた日立鉱山の山蔭に立てた、鉱山機械の修理工場だったという。しかし、実態は吹けば飛ぶような杉皮ぶきの粗末な丸太小屋だった。つまるところ、巨大企業日立も、もともとは一介の独創的な開発を宗とするベンチャー企業であったことを我々も思い出し、志高く前に進むようにしよう。

三木一克
元株式会社日立製作所 電力・電機開発研究所 所長
元株式会社日立製作所 機械研究所 所長
元株式会社日立メディコ 代表執行役 執行役社長
京都大学大学院工学研究科修士課程
1973年株式会社日立製作所入社 原子力研究所配属
1979年 京都大学工学博士学位取得
1981年 米国アルゴンヌ国立研究所 社費留学
1999年株式会社日立製作所 電力・電機開発研究所 副所長
2001年株式会社日立製作所 監査室 上席部長 事業部門・関連会社(国内、英国、中国)を監査、監査長3回・副監査長3回担当
2002年株式会社日立製作所 電力・電機開発研究所 所長 開発加速のため研究部制からプロジェクト制に開発体制を改革
2003年株式会社日立製作所 機械研究所 所長 研究拠点を土浦地区から事業部門が集中するひたちなか地区に移転
2005年株式会社日立メディコ 執行役常務 技術研究所を事業部設計部門に統合
2008年株式会社日立メディコ 代表執行役 執行役専務 日立グループ総合力発揮の場として医療システム開発センタを新設
2010年株式会社日立メディコ 代表執行役 執行役社長 超音波画像診断大手アロカ株式会社を完全子会社化、中国蘇州に生産拠点を新設
2012年株式会社日立メディコ 特別顧問